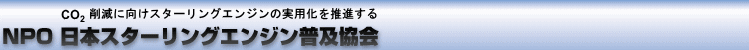◆第5回ビジネス懇話会報告 | |
1. 日時: 平成28年2月17日14:45〜17:00 | |
2. 場所: 都道府県会館407号室(東京都千代田区平河町2-6-3) | |
3.テーマ:“ストーブ発電Momo”とMOMOSEエンジン活用の呼びかけ
話題提供者:本協会理事長 鶴野省三
同副理事長・(株)JSE代表取締役 秋葉武志
同常務理事・(株)JSE取締役 清水政紀
| |
|
| 4.話題提供の発言要旨 |
|
今回の話題は“ストーブ発電Momo”の新聞記事(朝日新聞平成28年1月5日夕刊)を受けて、
「いかにしてスターリングエンジンビジネスを切り拓くか」について問題提起を試みたものです。
話題提供は添付パワーポイント資料を用いて鶴野→秋葉→清水のリレーで行われました。以下その発言要旨を記します。
| |
| | |
| | | |
| 4.1 |
ストーブ発電“Momo”と“JPE型”の紹介(鶴野) |
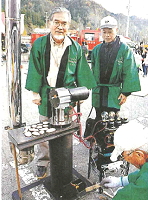 図1 ストーブ発電Momo
図1 ストーブ発電Momo
(高山市の展示会
平成27年10月) |
 図2 ストーブ発電JPE型
図2 ストーブ発電JPE型
(上田市の展示会
平成25年10月) |
|
| |
| |
ストーブ発電にはロケットストーブにSEを搭載した
“Momo”型と薪ストーブに搭載する“JPE型”があり、
これら製品の特長・性能の紹介と各ストーブ発電の用途及び使用方法の説明があった。 |
|
| | |
| 4.2 |
(株)JSE(秋葉) |
|
| |
|
次いで本協会会員有志で設立した(株)JSEの設立趣旨・設立経緯とその目指す
経営方針について説明がされた。 |
|
| |
| 4.3 |
ストーブ発電ビジネスへの取り組み(清水) |
|
| |
|
(株)JSEは百瀬機械設計(株)が目指すビジネスとは別に、
ストーブ発電Momo (図1)とJPE型(図2)の2機種の販売戦略の第1段階として、
市場開拓は長野県や岐阜・群馬等の山林や竹林で困っている問題解決に
ストーブ発電とMOMOSEグエンジンが活用できないかとの視点で市場開拓を行う。
またビジネスパートナーを探し、販売モデル案と販売モデル価格を示して、
市場開拓を進めながら普及促進決め手となる価格(値ごろ感)の感触を紹介した。
尚、詳細については
「ストーブ発電-ビジネス開拓について-」をご参照下さい。 |
|
|
| | |
5. | 質疑・討議 | |
|
討議は主として(ロケット)ストーブ発電Momoのマーケテイング(顧客は?;ニーズは?
競合製品との差別化;製造コストと売価など)について行われた。
その内容は、
「本邦初のSE商品を如何にして世に出していくか!」
のビジネスの入り口論であった。
| |
|
|
ストーブ発電の“市場・ニーズ・顧客” |
ロケットストーブ発電に対して市場ニーズがあるとは思えない、との否定的意見を皮切りに、多様な意見が交わされた。
問題は中小企業発の少量生産品であるため価格が高い。この障害を如何にして乗り越えるか。
この課題を念頭に議論が展開された。
|
| 論 点 |
課題・問題点 |
| | | |
| |
| 1. | ストーブ発電としてのニーズは? |
| ・ | 飛騨地方での大雪による長期間停電。 |
| ・ |
竹林の増殖対策… | 燃料として処理。 |
| | 今現在は燻蒸した松を林地に放置。 |
| | 長野県における長年の課題。 |
| ・ |
長野県:松くい虫被害の松の処理。 |
| ・ |
避難所での暖房・調理・発電機能として。 |
| ・ |
間伐材処理。 |
(これにはバイオマス発電の需要が高まっていて、近未来には資源不足になるとの指摘が出た。) |
| ・ |
避難所がニーズになるか ---------------------------> |
| | (ストーブ発電は暖房・調理・発電機能がある。 |
| | 非常用発電機は非常時に作動しないこともある。) |
| | ◎ |
物好きな富裕層への顧客開発…電卓は発売当初は
何十万円もする高価なものであった。
しかし今では100円ショップで買える時代。 |
| | ● |
趣味もニーズとなる! |
| | ・ |
自分の山小屋で使いたい。(本会会員) |
| | ・ |
オートキャンプで利用できるものがあれば需要は発生する。 |
| 2. |
ロケットストーブは無電源(コンセント無し)で高温燃焼が得られる。
それ故暖房と調理機能を持ったストーブとして利用されている。 |
| ・ |
そこに発電機能を加えると商品価値は高まる。 |
| (参考) |
無電源熱源機(例:コンセント無しのファンヒーター)の需要は多い。
廃熱発電技術として熱電素子があるが、実用化の見通しがない。
しかし、SEは利用可能。 |
| 3. | 発電機(SE単体)としてのニーズ? |
| ・ |
ソーラーパネルと同程度の価格ならば需要はある。 |
| ・ |
ヨットに搭載する自家発電機として魅力がある。内燃エンジン発電機は騒音が大きいので、静かなエンジンが欲しい。
以前わが国でもWhisperGen(ニュージーランド製)のエンジンが販売されていたが、価格が高すぎた。 |
| ・ |
ソーラーパネルや風力と組み合わせた商品開発は? |
| ・ |
バッテリー充電用としても利用できる ---------------> |
|
| | | |
| このようなニーズを有する自治体が顧客となりうるのではないか! | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ・ |
寒冷地ならば導入の意義はあるが、被害を予測しての購入に踏み切れるか。 | |
| ・ |
発電機能のみではカセットボンベ付きレシプロエンジン発電機に勝てない。 | |
| ・ |
プリウスを避難所の電源として利用する動きがある。 | |
| |
| |
|
ロケットストーブの弱点 |
|
|
薪や割れ竹などの燃料の燃焼が早く、火の面倒を見るために人が張り付かねばならない。 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
バッテリーには家庭用も含めて補助制度があるので、それを活用する方法も考えられるのではないか? | |
|
| 価格とビジネス |
| 質 疑 |
応 答 |
| | |
| ○ |
価格表を提示して説明したことは評価できるが、ビジネスの観点からの
詰めはどの程度か?すなわち価格体系(製造原価、販売形態による中間マージンなど)はどうなっているか。 |
|
|
| ○ |
ここまで仕上がってきているので、デザインや材料などを詰めた製造コスト、
PR・販促コストを詰める時期ではないか。 |
|
|
| | |
| ご指摘の意味での詰めはまだしていない。
資料
に示した「当初の価格」は現時点での販売価格。
「初期目標価格」と「希望価格」は現時点で聞き取りをした意見を参考に案出した目標価格である。
この目標価格でビジネスが成立させるように努力しなければならないと思っている。 |
|
|
SE協会が描くMOMOSEエンジンの将来像 |
MOMOSEエンジンのような小出力エンジン(300W~100Wまたはそれ以下)の最終的な用途は
工場等の廃熱回収発電であろうと考えています。その場合の200W級のSEの1個の価格は
コントローラー等を含めて5万円であればエンジン導入のメリットが出てくると考えています。
したがって、この目標に向けて“いま現在”を如何にすべきか。
それが私共の課題であると考えています。
|